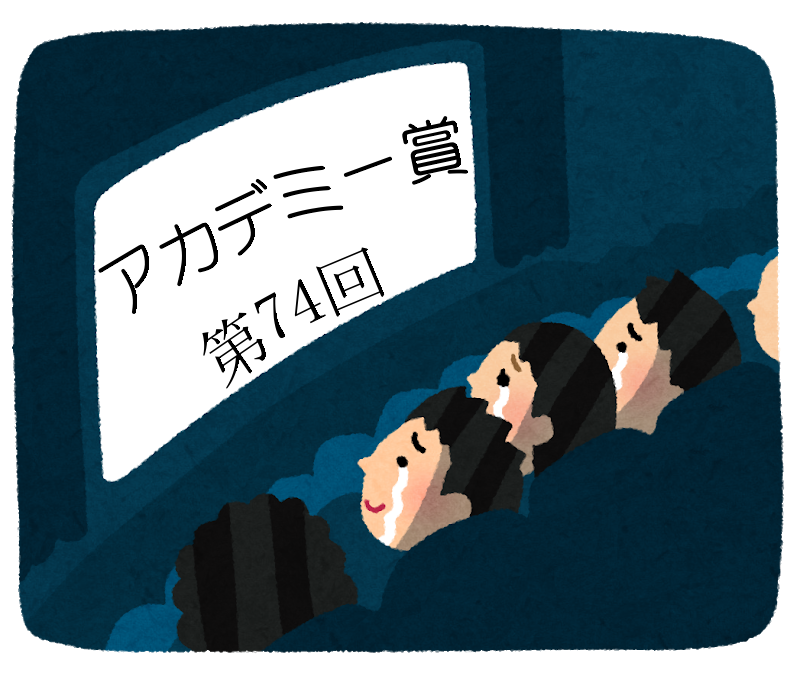日本の裁判員制度のニュースを見ているとこの時代のアメリカの裁判員制度にも満たないような報道がされているから、この映画を見せれば裁判員制度のどのようなものかを少しでもわかるのではなどと思ってしまう。
まぁ、かなり日本の裁判員制度とは違うのですが、分かりやすいと十二人の怒れる男は話をどのように詰めていけばよいのかを教えてくれるという点でも素晴らしい映画だと思う。
古い作品なのでオマージュの作品なのか似たようなタイトルがたくさんあるw
(この内容には、ネタバレがあります。)

ストーリー
一人の少年が父親を殺し、電気イス送りになるかの審議を陪審員である12人の男たちが話合をする。陪審員はみな少年の生死を決める話し合いには興味がなく、これからの野球を見に行くことや自分の工場の経営について、株の取引きなど全く関係ないことを考えていた。少年の生死を決める話し合いは投票で決めることになるが、みなが有罪に手を上げる中一人だけが無罪と言い出す。彼は無罪かはわからないが話合おうと言い出す。皆が自分のことだけを考えている中でただ一人、有罪であると断言できないために皆で話し合おうという。そこで皆がこの男性を説得するために一人ひとり意見を言い出すのだが、話し合いの中で証人や証拠についての疑問を検討し話し合うことで、ひとり、またひとりと意見が変わっていく。
感想
この作品はサスペンスとしての印象があり、作中での話し合いには伏線と解答の繰り返しにより、感情ではなく論理を積み上げることで終わりへと進んでいく。証拠や証人の発言に対して、それは正しかったのか?証人の発言に信頼できるのかを一つ一つを話し合いと検証がなされていく。
話し合いの流れには証拠に疑問を投げかけられ、その時は解決しなくても、後で話し合いで新たな答えに導かれていくという、疑問に対してすぐに答えがでるのではなく話し合いの末にこの解答があることによって12人達の話し合いは私たちに議論の上の結論であることを示している。
カメラは常に12人と同じ視点で演出されており、私たちに13番目の陪審員として参加している錯覚を感じさせている。有罪だと思っている私たちを本当に有罪なのか、この証拠は?、この証人の発言は?問いかけては証拠や証言へを否定していき、少年は無罪なのではないかと投げかけられ13人目の陪審員として私たちに考えさせる演出がされている。
作品は1時間30分だが、常に白熱した話し合いがなされているわけではなく、作品の中には休憩が行われたり雨が降ってきたり、途中でジョークを飛ばしたりと観客の熱を冷まし、話し合いによる論理的な説得が繰り返される。
もし、感情的で証拠とも証言とも関係のなく、意見を声高に叫ぼうものなら、終盤でスラムで生きた少年というだけで、決めつけて発言をした男のように誰一人として意見を聞いてはくれない。
同じ有罪と言っている人物も席を立ち背を向けるのだ。議論とは感情だけでは誰も納得させることができないことを教えてくれる。
作中には有罪であると感情的に怒鳴っている人物はいる、でもその人物は証拠と証言についての話をしているのであって、自分自身の好き嫌いだけを押し通すことはしていない、だからこそその人物の話は皆が聞いてくれる。
自身の感情任せに喚いた意見には、他の人物は意見を聞くような態勢を取らなくなる。ある人はテーブルに伏せていたり、ある者は席を離れ背を向ける顔を逸らす。
この作品では、無駄話や落書きをするようなことは一切が否定され話し合いがなされている。有罪の人の意見も無罪の人の意見もあるが証拠も証言も関係のない地震の感情的な意見は認められない。
登場人物のすべての人物が裁判に対して本気で向き合っているわけではないことも見逃せない。何名かの人物は話し合いで自分の意見をしっかりと発言しているわけではなく。なんとなくだったり、無罪が多数になったので意見を変えたりと真面目態度で裁判に参加をしてない人物もいる。その反対に自分の工場が危うい状況の中で裁判の内容をしっかりとメモをとり自らの考えによって有罪を主張している人物もいる。
作中で最初に無罪を主張する男は自らの意見に自信がなく、もしかしたら少年が犯人かもしれないという考えを持っていることを話すシーンがある。彼の言葉からは、自分に絶対の自信があるわけでも正義があるわけでもないが無罪の可能性があると主張しており、他の人物たちも同じである。
彼らには少年の無罪は関係がない。自分の考え方を貫き為に話し合いがなされている。始めは少年の生死が係っていることをこんなに簡単に決めてよいのかという主張をされているが、実際は自分の中の疑問の答えが見つからないために話し合いをしようと主張している。
2番目に無罪を主張する老人も始めに無罪をと言った人物の行動に賛同しているのであって少年に対しての同情をしていない。
移民やスラムに住んでいた人物もいるが、誰一人として少年には同情はしておらず、スラムで暮らしていた人物もその話をした後に行った投票では有罪の意見をかえておらず、この作品が感情や同情、似たような状況からくる贔屓などは一切なく話し合いの積み重ねによってのみ終わることを示唆している。
そのため、証言も証拠も怪しくなり、有罪を主張する人物がただ一人になったとき、無罪の主張する人たちは彼を厳しいまなざしで批判する。なぜこの裁判を有罪と主張するのかと、その11人の厳しいまなざしによって最後の人物が感傷的な理由で有罪を主張していることを暴露する。ここにこの作品のテーマとしての”話し合い”が見て取れる。
アメリカ社会での裁判の大切さ、そして話し合いとはどういったものなのかを見た人に教えてくれる作品
作品の最後に、2番目に無罪と主張した老人が最初に無罪を主張した人物に名前を聞く、そしてその場でそれ以上のことは発言せずに別れるシーンがある。彼らは仲間でも友でもなく少年の生死についての議論した関係以上ではないことを教えてくれる。
作品の構成を考えてみる
作中の流れをふりかえる
1名だけ無罪を主張する
↓
話し合いが行われるが無罪を主張した人物は可能性のみを語る。
↓
投票が行われ、2人目の無罪の主張
↓
2人目の人物の意見によって証言を検証する
↓
投票が行われ、3人目の無罪を主張する人物が出てくる
↓
無罪6対有罪6になり無罪が有利になる。
↓
とこのように話が展開していく、
序盤
最初に無罪を主張した人物の発言は少年が犯罪をしていない可能性についての話しかできておらず、強い主張はされていない。
中盤
2人目の無罪を主張する人物が発言により、証拠や証言に対して検証がされていく。
終盤
皆の意見が無罪になる。
作品の根底には話し合いの繰り返しによっての論理の積み重ねの重要視しているが、最初は可能性についての反論しかできないが、仲間が増えていくことによって曖昧や可能性についてではなく、事実についての検証が行われる。
可能性について段階で、観客にどのような裁判でどういった証拠や証言が出てきたのかを示し、そこに投票が行われることで見ている観客も13番目の陪審員として有罪、無罪を考える機会を与え作品の中へと引き込んでいく。
そのために2人目の無罪を主張する人物が出てくるまで証拠や証言の可能性についてを語り、観客が二度目の投票で有罪と判断したところを、話し合いによって論理を積み重ねることによって観客の考えを変えていくのである。
この作品のモチーフは”話し合い”であり、話し合いによってのみ作品が進むことを繰り返し主張されている。
ビジュジアルデザイン
ライテングを見てみると、この作品自体がかなり古く1957年と白黒映画の時代であるためにカット数はとても少ない、しかし、白黒であるからこそ光と影の演出が大切になっている。この作品は一つの部屋のみで完結しており、他の部屋は唯一トイレのシーンがあるのみで、トイレのシーンと話し合いをしている部屋のシーンを見比べるとライテングがまるで違う。
トイレは全体が照らされており、少しくらいが隅まで見えるようになっているが、話し合いの部屋ではテーブルだけが光を反射しており、天井や床、壁の端などは影に隠れてぼんやりとしている。
この部屋で重要なのは12人の男たちのみであり、部屋の装飾やディティールは見える必要すらない。テーブルに光を当てることで囲っている男たちのみ観客の視線を集まるように演出されている。
また、突きつけた証拠に反論されたときに影が強くなるといった演出がされることでその人物の心境の変化を演出しされている。
音響
この作品では、ほぼ音楽がかかっていない。心境の変化などを表す演出として短い曲は流れるが、重要なのは俳優の声の強弱である、そこに込められるイントネーションの変化である。
そのため、ほんの数回音楽が挿入されるだけになっている。これは効果音も同じで、扇風機が動くシーンで動く音が入ってもおかしくはないが、観客の意識を俳優の声にだけ意識させるために入れられていない。